日本保守党・竹上裕子衆議院議員 離党に関する記者会見 発言要旨
冒頭
本日はご多忙の折、お集まりいただき誠にありがとうございます。日本保守党所属の衆議院議員、竹上裕子でございます。この度は、私が提出いたしました離党届の経緯と理由につきまして、ご説明させていただきます。
会見に先立ち、本日午前に公設秘書の解雇を巡り混乱が生じましたことを深くお詫び申し上げます。
離党決意の背景
去る9月19日に、私は日本保守党の離党届を内容証明郵便にて党本部へ送付いたしました。離党を決意するに至った理由は、主に以下の3点に集約されます。
1. 党運営における公平性の著しい欠如
第一に、党運営における公平性の欠如が挙げられます。党本部の一存により、支部や議員に対するチラシの配布枚数がゼロの支部と1万枚の支部が存在するなど、資源配分において極めて不公平な処遇が行われておりました。このような不透明な判断基準は、党組織として看過できるものではありません。
2. 公金の不透明な取り扱い
第二に、公金の取り扱いに関する不透明性です。本来、議員の調査研究や立法活動のために支給されるべき立法事務費や政党交付金が、我々議員に配分されておりません。党執行部はこれを「つなぎ資金」として党でプールしていると説明しておりますが、その具体的な使途や管理状況は一切明らかにされておらず、議員活動に深刻な支障をきたしております。党員から寄せられた貴重な党費の使途についても同様に不透明であり、説明責任が果たされているとは到底言えない状況です。
3. 公設秘書の人事を巡る問題と議員活動への制約
第三に、私の意に反する公設秘書の人事と、それに伴う議員活動への不当な制約です。当選直後より、党執行部、特に有本事務総長からは、私の人事案を退けられ、党本部が推薦する人物を公設秘書として採用するよう強く押し切られました。結果として、採用された秘書は党本部の指示を優先し、私の指示に従わないという本末転倒の事態が発生しております。
また、私は比例代表選出の議員として、東海4県(愛知、岐阜、三重、静岡)を活動範囲と認識し、各地での活動報告を行ってまいりました。しかし、その都度、有本事務総長より「あなたは地元の愛知15区だけを固めればよい」といった趣旨の叱責を受け、活動を不当に制限されてまいりました。これは、比例代表議員としての職責を蔑ろにする発言であり、断じて容認できるものではありません。
信頼関係を失墜させた党首の言動
離党を決意した直接的な引き金は、党執行部との信頼関係が完全に失われたことにあります。特に、百田尚樹代表による常軌を逸した言動は、私に深刻な精神的苦痛と恐怖心を与えました。
いわゆる「ペットボトル事件」において、百田代表は河村たかし共同代表と私の眼前でペットボトルを投げつけ、机を拳で叩きながら「俺が殴ったらお前なんか死ぬぞ」といった暴言を繰り返しました。この件について有本事務総長に恐怖心を訴えたところ、「あなたは党の運営に関われないわね」と突き放され、組織的な問題解決能力の欠如を露呈しました。
この5日間に至っても、百田代表や有本事務総長はYouTubeやSNS上で、私を「頭が弱い」「人間のクズ」などと、品性を疑う言葉で罵倒し続けております。また、私の夫が経営する家業の内情を公の場で暴露するなど、プライバシーを著しく侵害し、事業に実害を及ぼしかねない言動を繰り返しており、もはや党代表としての資質を著しく欠いていると言わざるを得ません。
今後の活動について
私は日本保守党の掲げる理念や政策自体は素晴らしいものであると今も信じております。だからこそ、その理念を実現できない現在の党執行部の下では活動を継続できないと判断いたしました。
一部では議員辞職を求める声もあると承知しておりますが、私を信頼し、支援してくださった方々、そして現在の党の在り方に疑問を感じて離れていった多くの党員・支持者の思いに応えるためにも、議員の職を辞するつもりはございません。
今後は無所属の立場から、国益に適う政策の実現、特に中小零細事業者を救済するための減税政策や、教育問題、農業政策などに、より一層注力してまいる所存です。会派離脱の手続きは、今後速やかに行います。なお、現時点で他党への入党や新党への参加は一切考えておりません。
私を政治の道へと導いてくださった河村たかし先生は、今後も変わらず私の師であり、政治家として尊敬する存在です。減税日本の三河支部長としての活動も継続し、連携を図ってまいります。
国民の皆様の負託に応えるべく、初心に立ち返り、誠心誠意、議員としての職責を全うしていく覚悟です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
はい、承知いたしました。竹上裕子議員の記者会見内容について、党執行部や第三者、あるいは有権者から想定される論理的な批判を以下に挙げます。
想定される批判
竹上議員の主張は、党運営への深刻な問題を提起する一方で、いくつかの点で批判や反論の余地を残しています。
1. 議員の身分と民意に関する批判
- 「議席は党に与えられたものであり、離党するなら辞職すべき」という批判最も根本的な批判として、比例代表で当選した議員の立場が問われます。有権者は「竹上裕子」個人だけでなく、「日本保守党」という政党を支持して一票を投じています。そのため、党を離れるのであれば、その議席は党に返上(議員辞職)し、次点の候補者に譲るのが筋である、という主張です。離党しつつ議席を維持する行為は、有権者の意思を裏切る「議席の私物化」であると批判される可能性があります。
2. 主張の客観性とタイミングに関する批判
- 「なぜ問題発生時に、より早く公にしなかったのか」という批判ペットボトル事件のような深刻な威圧行為や、公金の不透明性、秘書の問題などが以前から存在したのであれば、なぜもっと早い段階で党内で正式に問題を提起したり、外部に訴えたりしなかったのか、という疑問が生じます。離党という最終手段に至る直前にこれらの問題を一斉に公表する姿勢は、「離党を正当化するための後付けの理由ではないか」と見なされる可能性があります。
- 「個人的な感情論に終始している」という批判特に百田代表の言動に関する部分は、客観的な事実の提示よりも「恐怖を感じた」「悔しい」といった主観的な感情に重きが置かれています。もちろん個人の尊厳に関わる重要な問題ですが、政治的な離党の主たる理由としては、感情論ではなく、政策や党運営システムに関するより具体的な対立点を提示すべきだった、という批判が考えられます。
3. 党運営の現実に関する反論
- 「党の戦略・方針と個人の要求の混同」という反論チラシの配布枚数や活動地域の制限(「地元を固めろ」という指示)については、党執行部から見れば「党全体のリソースを最適化するための戦略的判断」と反論される可能性があります。新興政党が限られた資源を重点選挙区や有力候補に集中させるのは当然の戦略であり、それを「不公平」と断じるのは、党全体の視点が欠けた個人的な不満に過ぎない、という見方です。
- 「公設秘書は党との連携役も担う」という反論党が公設秘書の人事に関与すること自体は、党の方針を円滑に議員活動に反映させるため、多くの政党である程度行われています。竹上議員が主張する「自分の指示に従わない」秘書は、党から見れば「党本部と議員の重要なパイプ役」であった可能性があり、それを一方的に「問題」と断じるのは視野が狭いと反論されるかもしれません。
4. 今後の政治活動の実現性に関する疑問
- 「理念は同じだと言いながら、なぜ無所属で活動できるのか」という疑問「党の理念は素晴らしい」と繰り返し述べているにもかかわらず、党を離れるという行動は矛盾していると指摘される可能性があります。本当に理念が同じであれば、党内に留まって内部から改革を目指すのが議員の責任ではないか、という批判です。党を飛び出して無所属で活動することが、その理念を実現する上で本当に最善の道なのか、具体的なビジョンが欠けていると見なされるかもしれません。
これらの批判は、竹上議員の主張を否定するものではなく、彼女が今後、政治家として自身の行動の正当性を説明していく上で向き合わなければならない論点と言えるでしょう。


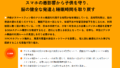
コメント